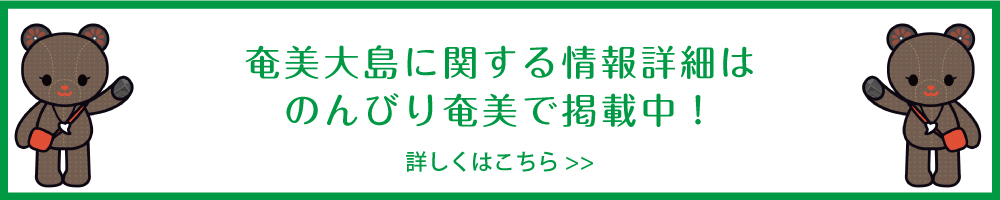Like a Rolling Stone!! 転がり続ける石のように、偶然を生み出す。島がちゃ本舗:元井庸介
島人
2016/03/08
三谷晶子

「本当、アホの固まりのような気持ちで東京に行ったんです」
どうして、上京したの? と聞くと、元井さんは開口一番そう言った。
奄美大島、住用町生まれ。18歳で、大学進学のために上京した。
「高校生の時に友達とオムニバスCDを作って、それがすごく楽しくて。東京に行ったら、音楽で食べていくことができるかも、なんて思ったんですよね」
進学した大学では民族音楽の研究もあり、それはそれで楽しかったけれど、とにかく東京に馴染めなかったと、元井さんは語る。
「流行の移り変わりの速さがまずよくわかりませんでした。好きなものは好きでいいのに、どんどん『これがイケてる』とファッションも音楽も変わっていくことが」
東京の方がやりたいことができる、と思っていたけれど、何だか違う。そう思ったときに、大学の卒業論文の〆切がやってきた。
「比較文化学科という学部で、民俗学の研究をしていたんです。奄美にしかないものを取り上げようと思って針突(ハズキ)という手に入れるイレズミのことを調べ始めました。ところが、関東には文献が全くないんです」
あちこちの図書館に問合せ、右往左往を繰り返した。困り果てて、島の友人に電話をした。すると、「隣の集落に針突をしている人がいたよ」という話を聞いた。
「自分の一番興味のあるものが、島にはすぐ隣にある。何だか脱力したような気分になりましたね」
大学を卒業後、音楽を紹介するWebサイトの編集部でライターとして勤め始めた。あちこちのライブハウスに足を運び、CDを聞き、レビューを書く日々。
最初は好きな音楽に触れられる仕事だ、と思っていた。けれど、それ以上に、好きではない音楽を聴くことも多い仕事だと、すぐに気付いた。勤め始めて数年するうちに、好きだった音楽を聴いても心が動かなくなってきたという。
「そんな時に、UAのライブで「太陽ぬ落てぃまぐれ(てぃだぬうてぃまぐれ)」を聞いたんです」
ルーツを奄美群島・加計呂麻島に持つUAも自分の音楽の方向性に悩み、シマ唄のレジェンド朝崎郁恵に師事して、奄美のシマ唄を歌いだした。
「太陽ぬ落てぃまぐれ」は、奄美大島のシマ唄。奄美の言葉で「太陽が落ちる間際」を意味する。
歌を耳にした瞬間、鳥肌がたった、と元井さんは言う。
「帰らなきゃ、と思いました。自分のルーツが島にあると知っているのに、どうして俺はここにいるんだろう、と」
島に戻って数か月は、山や海で遊んでゆっくりと過ごした。そして、奄美市と大和村を対象に放送するコミュニティFM、あまみFMに勤務し、番組の企画制作とディレクターを勤める。
それから、5年後、独立を決めた。

「人口はどんどん減るばかり。内地にいる皆も、島に帰りたいと言うけれど、仕事がない。だったら、自分で仕事をやるやつが増えるべきだ。だけど、俺は、今、自分でやってない。そう思うと、独立しなきゃ、と思いました」
独立を考えた時点で、現在、取り組んでいる島がちゃ本舗の構想はあったという。
「島の面白いこと、伝えたいことはいっぱいある。マニアックになり過ぎず、ポップに楽しんでもらうには、と思うとガチャガチャが面白いかな、と」

島がちゃの中身は、まずは、サタ豆に決めた。サタ豆は島に自生する地豆に黒糖をまとわせたもので、島内の集落それぞれ、また生産者によって味が変わる。奄美大島では、集落によりシマ唄の節や方言も違う。その集落の特徴がわかるようなリーフレットを付けて、ガチャガチャの中身にすることにした。
ガチャガチャが完成し、一番最初に置いてもらったのは奄美大島の北部、笠利町にある奄美リゾートばしゃ山ホテル。
自分の思い描いていたものが形になったという感慨もありつつ、ホテルの前にガチャガチャがあるという状況があまりにもシュールで、何だか笑ってしまったそうだ。
そのうち、奄美大島空港や、島内・島外で行われるイベント、結婚式などでの需要が増えてきた。
子どもから家族連れ、お年寄りから若いカップルまでがそれぞれの形で島がちゃを楽しみ、時には島がちゃと一緒に撮った写真を送ってくれるという。

「島がちゃが何だか自分の分身のように思えるんですよ。島内・島外に、自分の分身があって、ガチャガチャを引くと、そこから『島がちゃで出た集落に行ってみようかな』と思う人がいたりして」
そもそも、島の魅力は偶発性、偶然の出会いだ、と元井さんは言う。
道を聞いたら、「お茶でも飲んでいけ」と言われる。立ち話をしたら、果物や野菜を手渡される。そして、思わぬ人や場所を紹介される。

「ガチャガチャも何が出るかわからない偶発的なもの。島の人と、ガチャを引いた人との偶然の出会いのきっかけに島がちゃがなれたら嬉しいですね」
出会いはいつも偶然で、そこから何が始まるのかは想像もつかない。偶発的に始まった動きが、いつか大きなムーブメントになるかもしれない。
偶然が生む必然は、誰の手元に届くだろうか?
転がり続ける石のように、元井さんの思いが詰まった島がちゃは、今日も誰かに手渡されていく。
この記事を書いたフォトライター

三谷晶子
作家、ILAND identityプロデューサー。著作に『ろくでなし6TEEN』(小学館)、『腹黒い11人の女』(yours-store)。短編小説『こうげ帖』、『海の上に浮かぶ森のような島は』。2013年、奄美諸島加計呂麻島に移住。小説・コラムの執筆活動をしつつ、2015年加計呂麻島をテーマとしたアパレルブランド、ILAND identityを開始。