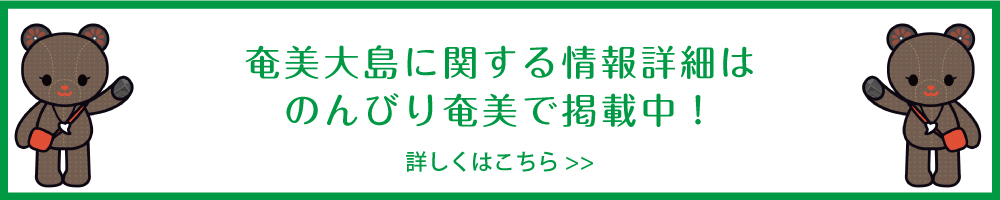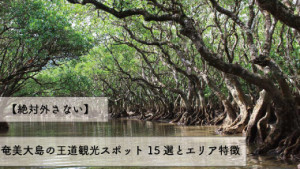点と点を紡ぐ、世界に誇る職人をたずねて龍郷町へ〜大島紬養成所での出会い〜
島コト
2017/12/28
秋葉 深起子
「カラカラカラ…バッタンバッタン」
大島紬を織る、機(はた)の音。
幼いとき、近所から当たり前のように聞こえた心地よい音。
しかし、生産反数の減少に伴い、今ではこの音を“懐かしい”と感じる人さえも少なくなっているようです。
ここは大島紬の発祥の地、奄美大島。
大島紬を織る「織工(おりこう)」さんを育成する「大島紬養成所」は現在島内に5カ所あるそうです。
幾人もの職人の手を経て、最後の仕上げとなる織りの工程。大切な役割を担う織工さんに会いに、今回は龍郷町にある2つの養成所へ伺ってきました。
奄美大島の原風景を感じる嘉渡の養成所

まず訪れたのが、龍郷町の嘉渡(かど)集落にある養成所。
奄美大島に住んでいる人でも、嘉渡へ行ったことがない方は多いかもしれません。しかし実は、大島紬古典柄の代表図柄「龍郷柄」発祥の地が嘉渡なんです。
ソテツの葉とハブを図案化した連続模様「龍郷柄」は今もなお人気で、大島紬を代表する柄なのです。 
現在、この嘉渡の大島紬織工養成所には4名の織工さんがいて、
土日を除く週5日間、「龍郷柄の大島紬」を織っているそう。
大島紬のうりぎょらさ(大島紬の織りの美しいこと)

これも。

これも。
すべて「龍郷柄」です。
先染め手織りの大島紬は、同じ龍郷柄でも柄の大きさ細かさ、糸(柄)の色などによって、印象がまったく違います。
そしてこの柄は複雑な先染めの工程によって染められた、糸の「点」が交わり重なり合ってできているもの。それが世界一繊細、とも言われる大島紬の特徴の1つでもあります。
すべてが唯一無二の「うりぎょらさ」なのです。

これらを織る女性たちは、普通の学校を卒業したあとに織工になり、そのまま数十年にわたり大島紬を織り続けている人や、一度は機織りをやめて他の仕事についたものの、また織りはじめたという織工さんなど、それぞれの物語を持っています。
彼女たちの指先から紡ぎ出される美しい織物を見ていると、
この世界一の職人技を見るだけでも、嘉渡に来た価値がある、と感じました。

施設の見学は自由とのこと。
伝統工芸士である今村曉子先生が、
「いつでもいらして大丈夫ですよ。」
と笑顔でおっしゃってくださいました。
興味のある方は、貴重な職人技を見学できる嘉渡の大島紬織工養成所へぜひ一度いらしてみてください。
最高の環境で世界一の技術を学べる瀬留(せどめ)の養成所
 続いて、龍郷町のもう1つの養成所、瀬留(せどめ)にある大島紬技能者養成所をご紹介します。
続いて、龍郷町のもう1つの養成所、瀬留(せどめ)にある大島紬技能者養成所をご紹介します。

訪れた日は、9名の織工さんたちが大島紬を織っていました。

写真では「音」を伝えられないのが残念ですが、糸繰りの回る音もまた懐かしく、動画も撮影。
私の頭の中では、大好きなシマ唄「糸くり節」のメロディー。
これこそ、島を感じる風景。

介護のお仕事を辞めて、大島紬を織り始めて8年目という織工さんにお話をお聞きしました。
「若いときに(織工である母に)一度教えてもらったことはあったけれど、そのときは厳しくて続かなかったの。それから数十年して、織工を始めたらもう楽しくて、楽しくて!
緻密で繊細な大島紬を織るのは簡単ではないけれど、織りあげたときの達成感や、難しい柄に挑戦するときの気持ちのワクワク感はとても刺激的でたまらない。
環境も良く楽しい仲間と一緒だから、ここ(養成所)に来るのが毎日楽しみ!」
織工さんとしての大先輩であるお母様は90歳代で現役!
いつか、一緒に大島紬を織ってみたいですね、とのこと。
素敵なお話に、胸がキュンとしました。
こんな贅沢なことを学べる場所があるなんて最高な島!
 こちらは「大島紬を織ってみたい!」と、埼玉県から移住した女性に、伝統工芸士である森節代先生が丁寧に教えていらっしゃいます。
こちらは「大島紬を織ってみたい!」と、埼玉県から移住した女性に、伝統工芸士である森節代先生が丁寧に教えていらっしゃいます。
そう、ここは「大島紬の養成所」。
初心者であっても「大島紬を織ってみたい!織工になりたい!」という熱い思いをもった方に、織り方を教えています。
埼玉県から龍郷町に移住し、養成所に通って2年の女性は
「今まで大島紬とはまったく別の業界で仕事をしていたけど、昔から憧れの大島紬を織ってみたくて。探したら、ここの養成所を教えてもらったのです。」と。
龍郷町に住所がある人であれば、習いたいときにいつからでも「大島紬の織り」を学べる龍郷町の養成所には、日本各地から大島紬の織りを学びたいという問合せがあるそう。

手元を覗いてみると・・・とっても美しい大島紬!
習い始めて2年で、これほどのものを織っていることに驚きました。
しかも、この紬で2反目だそうです!
(人生初の“自分で織った大島紬”のお写真も見せていただきました。)
「いろんな習い事などがある中で、最高級の大島紬の織りをこんなに丁寧に習うことができるなんて!しかも、本場 奄美大島の龍郷町で学べるなんて、こんなに贅沢なことはないですね。
本当に最高の環境で最高の技術を教えていただいて毎日楽しいんです!!いつか先生のような素敵な大島を織ってみたいです。」
とお話してくださいました。

森先生が織っていた、9マルキの総絣。
どのように点と点が合って柄になっていくのか、近くで見ていても理解ができないくらいの緻密さ。
さすがの美しさに見惚れてしまうとともに、やはり大島紬の織りは世界一緻密で繊細なのだと感じることができました。

(休憩時間には、大島紬以外のお話も盛り上がり、この時間が毎日通う楽しみの1つにも!)
どこの伝統工芸の世界でも“後継者不足”と言われていますが、
『大島紬の織工さんになりたい』という方は、意外といるそうです。
でも問題は、大島紬の織工としてだけでは生活ができないということ。
大島紬に惚れて奄美大島に移住してきてくれた後継者希望の方たちが、(生活できずに)やむを得ず、本土に戻ってしまうことも、少なくないそう。改めて、伝統工芸を守り続けていくことの大変さを知ることができました。
糸繰りが教えてくれること
奄美大島の有名なシマ唄「糸くり節」。
『糸繰りの糸は切れたら結びなおすことができるが、
人の縁は切れたら、結びなおすことができません』という歌詞。
大島紬の伝統を引き継ぎたいという方とのご縁が切れないよう、私たちも考え続け、できることを行動しなくてはいけないと感じました。
世界唯一の職人さんたちがいる龍郷町の2つの養成所は月曜から金曜午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始、お盆は休み)見学が可能とのこと。
また、養成所に通いたい方は龍郷町の商工会で受け付けているそうです。
この記事を書いたフォトライター

秋葉 深起子
RDA(Relaxing Days Amami)ツアースタイリスト。東京でカラー&イメージコンサルタントとして、企業研修や講演、プロダクトデザインのカラー提案、フォトスタイリング等を行う株式会社アンドカラーを設立。2017年「五感を刺激する大人のための奄美旅」をモットーに、奄美と出会えてよかったと思えるような旅やイベントを企画運営事業を開始。